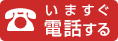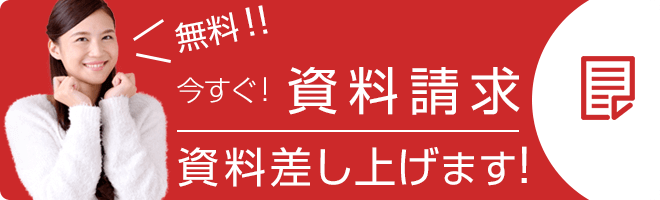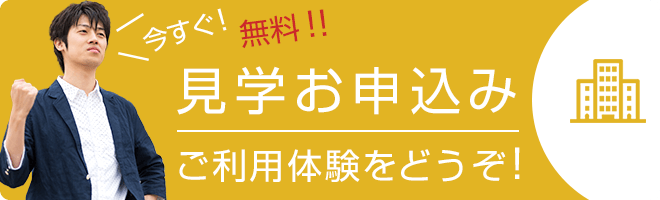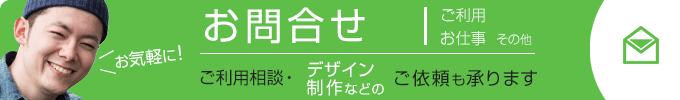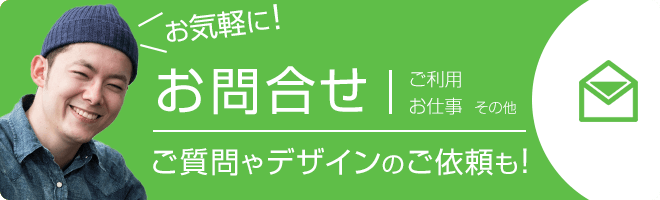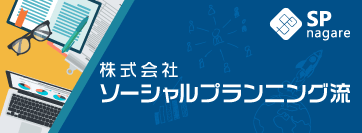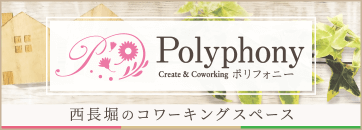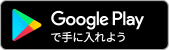こんにちは坂根です
先日、なぜかザ・シンフォニーホールというあのカラヤンも褒めたクラシック専用ホールでマネジメントについて話す機会がありました。
人前で話すので、今までの「せふぃろと」とか「ダイアロゴス」とかの法人での取り組みをマネジメントという視点で考えなおす機会になりました。
マネジメントですが人とか会社とかでの管理者の方法の事で、有名なところによると、「もしドラ」という小説がベストセラーになったあれです。
 |
![]()
僕も独立してからかれこれ10年が経ちまして、振り返るとマネジメントについて右往左往してきたわけだけですけども、やってこれた理由としては、一番は「運」が良かった事と、「人のよい方々ととの出会い」に恵まれた事が大きいと本気で思います。
ただ、結果論としては、今のところですが上手くいっているのはそれ相応の理由があるわけです。
ひとつに、人を大事にしょうとしてきたこと。
欲深くならないこと、たんなるうまい話しを持ってくる人とはあまり付き合わなかった(会社を経営する為であっても人付き合いにあせらなかった)ことがざっくりとはあると思います。
そしてもう一つが会社経営の事など何もわからなくても、上手くいっているのは、福祉的な技法、ソーシャルワークの技法が実はマネジメントに有効だったからだと思います。
ソーシャルワークにおいてグループの取り組みでグループが目標に向かって、実現傾向を発揮するには、
①共感的な理解
②無条件の肯定的な関心
③自己一致、誠実さ、純粋性
※カールロジャースの三原則
があり、これを日常生活や協働作業領域においても実現できる空間づくりを目指してきました。
実際のところ、様々な人たちが集っているので、そのようないい空間ができた事はまれですし、今も全然ちがったりしますが、少なくとも僕というリーダーはそれを目指していたわけです。
また、職員の管理や育成においても、ソーシャルワークにはスーパービジョンという方法論があります。本人の主体性を尊重しながら進める方法論など、マネジメントにも当然ながら有効な方法論などが沢山あるわけです。
ソーシャルワークにおいては、クライエントや社会のニーズを掘り起こし、社会資源を調整・開発しコーディネートする事が仕事です。
これはマネジメントそのものですよね。
・マネジメントの流行?
高度経済成長の時代は終わり、マネジメントの方法も変化してきていると思います。
マネジメントは組織のミッションを遂行するために組織を最適化しその組織に合った人材を採用・育成し組織に適合させる方法から、職員個々の様々な価値感や生き方を支えるために企業活動を行いそれぞれの居場所や役割を発揮できるようにする方法に変化してきていると思っています。
僕らの法人はそもそも不器用な職員やメンバーさんと一緒に、そのような考え方でやってきて、時代もそのようになってきたので、自然に時代の流れに合っていたように思います。
・ソーシャルな事業をする企業としてのマネジメント
今、過渡的な状況下にあって、組織のミッションか個人の生き方を尊重するのか?でマネジメントが揺らいでいる。ような気がしています。
そして、僕らがやっているのはソーシャルな事業です。
本来の企業のあり方とも違います。
本来、普通の営利企業は、事業ドメインは利益の最大化、継続企業(ゴーイングコンサーン)としての前提を果たすために決定されるものです。しかしソーシャルエンタープライズや非営利組織は社会的な課題へのミッションの遂行や達成・改善・リレーションシップが目的で、その都度、目的に合った事業ドメインが選択され決定される。社会的なミッションそのものは時代や社会変化とともに必要性を失うことも多く、継続性よりも断続的に現れる場合もあります。ソーシャルセクターはそもそも継続企業たりえない組織だと思います。※ちなみに営利企業にとっての外部環境も変化の激しい時代となっており同じ状況や課題が出てきています。
ソーシャルセクターを生業とするとその組織に従事する人たちはその仕事で生計をたてる。そこの職員はその仕事で結婚し子どもを育て、生活していく事になると、その生活を守っていかねばならなくなる。そうなると組織はミッションの遂行ではなく、営利企業と同じように継続していく事が目的に変化する事になり、組織の風土が淀んできます。そうやってゾンビなNPOができあがる事になります。
そうならない為の方法のひとつとして、スペシャリスト(専門職化・職人化)がこれからの時代には必要なのだと思います。
これからは、地縁に縛られたコミュニティに所属したり、固定的な会社に所属して自分の社会的位置を確保していくという方法ではなく、様々な地縁であったりそれを離れたアソシエーションに所属しながら、自分の社会的な居場所や役割を自由に移動しつつ繋がりあい、棲み分けしながら生きていくことになるのだと思います。
おそらく、マネジメントも、会社に縛られ組織的ミッションを遂行していくよりも、個人個人が専門性や自らのモチベーションを活かし主体的に活動しながら、プロジェクトごとのミッションに対してその都度集合してマネジメントしていく事が主流になると核心しています。
「せふぃろと」とか「ダイアロゴス」を運営していく上でもそのような変化を踏まえながらやっていかないといけないなぁ~と思っているところです。
職人的な仕事の復活と専門職の養成の流れの中で、まずは、専門職や職人を養成していくこと、ソーシャルワークとして行ってきた職員やメンバーさんがが主体性を発揮する事を支える集団をしっかり作っていくことが大切だとおもいます。